 |
   |
| No. |
 |
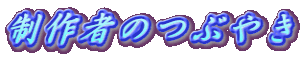 |
| 01 |
|
・ 壺
壺は、縄文時代の初期に現れており、
以後、水や酒を入れる実用的な道具、
または装飾品として作られてきました。
墨壺、茶壺、骨壺なども。
|
| 02 |
|
| 03 |
|
| 04 |
|
・ 徳利と盃
徳利と盃(さかずき)は、いずれも酒の容器。
徳利の別名「ちょうし(銚子)」は、
本来神道の結婚式に用いた長い柄の器のこと。
盃は、別名「ちょこ(猪口)」とも。
|
| 05 |
|
| 06 |
|
| 07 |
|
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
・ 湯のみ茶碗
集合写真。 |
| 17 |
 |
・ 湯のみ茶碗
ひょうたんを二分して加工し、
小型の湯のみ茶碗に仕立てました。
色柄は、自己流で思い付くままに。
おままごと用品(?)です。 |
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
・ ボウリング・ピン
小型ひょうたんを、ボウリングのピンに見立てました。
秋に新しいひょうたんができたら10本そろえたいと思います。 |
 |
   |
![]()